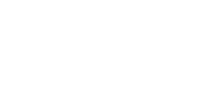「ユーザーが求めるモノをつくる」

初代Hi-Motion
「ハイビジョン対応のハイスピードカメラを開発できないか」
ある放送局からそんな話が持ち込まれたのは2003年のこと。ちょうどこの少し前頃から映画やCMなどでのハイスピードシーン撮影で、本来は実験、計測用のナックの工業用ハイスピードカメラが使用される例が増えていた。一方、放送業界ではハイビジョン対応機器が次々と開発される中、ハイスピードカメラだけはハイビジョン対応が大きく遅れており、ハイスピードシーンのみを旧機種で撮影して差し込むといったワークフローが取られていた。そこで「おたくの持つ技術を利用すれば、放送用のハイスピードカメラがつくれるのでは」とナックに白羽の矢が立ったというわけだ。
ナックは映像制作業界向けに海外の映像機器メーカーの代理店として、シネ用カメラ、レンズ、三脚などを輸入販売・レンタルしていたが、メーカーという立場でこの制作分野向けのカメラ開発を行ったことがなかった。営業サイドでは放送用ハイスピードカメラの製品開発を行うことで、新たな分野への事業展開を進めたいという強い思いはあったが、開発そのものがチャレンジであると同時に「仮にカメラを開発できても、マーケットが限られビジネスとしての発展は難しいのではないか」、「工業用製品の開発に専念すべきではないか」という意見が社内の大勢を占めていた。
しかし、営業サイドでは何としてもこの製品開発を推し進めたいという強い信念の元、粘り強く社内調整を繰り返した。その結果、「今まで我々はユーザーの求めに応じて製品や技術を開発してきた。『お客様が欲しい物をつくる』、そうして我々は成長してきた」と当時の経営陣は最終的にハイビジョン対応ハイスピードカメラの開発を決断する。ただし、社内の多くのリソースをそこに割くことはできない。開発の条件として提示されたのが、顧客との折衝は営業1名で対応、技術陣もごく数名、しかも通常業務と並行して行うというものだった。
やがてこのプロジェクトのキーパーソンとなる技術担当の後藤正勝は、この当時、視線計測用非接触アイマークレコーダーの最新機種の開発に関わっていた。もちろん放送用のハイスピードカメラの開発が進められていることは知っていた。だが「営業と技術が何か夜遅くまでずいぶんと打ち合わせしているなぁ」程度の認識。同じ技術部内の後藤にしてその程度、である。後に、アメリカテレビ芸術アカデミーがその功績を評価し、技術・工学エミー賞を授与することになるHi-Motionの開発は、実は社内でさして光が当てられたわけでもなく、開発部門の片隅でごく静かにスタートした。

エミー賞のトロフィーと盾。