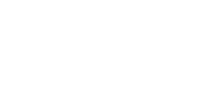「可能性を諦めない」
フィルムからデジタルへ。名取はアナログからデジタルへの過渡期、そしてデジタル全盛へと移り変わった時代、そのすべてをエンジニアとして経験してきた。映像の世界の中でもレンズはその基本構造は大きく変わっておらず、デジタル化における変化は少ない分野だとされる。とはいえピントやズーミングなどの電子制御、手ぶれ補正機能など、この間いくつもの新しい技術が導入されてきた。
そんな技術変化に対応するのは大変ではないか。そう名取に問うと意外な答えが返ってきた。
「新しいレンズは技術的な情報も揃っていますから調べればすぐに対応できます。むしろ古いレンズにいかにきちんと対応できるかですね」
デジタル化の進展が進む中、実は映像制作の現場では今、レトロレンズのニーズが大きく高まっている。特に映画やCMなどの分野ではあえてレトロレンズを使い、ボケやフレアといった映像への“味わい”を求める動きがあり、その傾向はどんどん増えてきているのだ。

機械加工室で作業する名取。入手が難しくなったレンズ部品などをここで自作し数々のレトロレンズを生き返らせてきた。

金属製の部品はフォーカスフォロワーとカムシャフト。黒色のリング状の物はレンズ分解工具。いずれもサイズを正確に計測して図面を起こし、名取自身が手作業で仕上げた。

そのため名取の元にも近年、入社以前に販売されたレンズのメンテナンスが数多く持ち込まれる。古いレンズは図面がないどころか、もうすでにメーカーも存在しないものもある。当然修理のための部品はないし、レンズそのものを分解する工具もない場合も多いという。
部品調達が難しくなった製品は「サポート終了のため修理は受けつけません」という対応が取られるのが一般的だ。特に製品のライフサイクルが早くなっている現在、発売開始からサポート終了までの期間はどんどん短くなっている傾向にある。そんな時代にあって、名取ら制作技術グループの対応は「可能性を最後まで探る」「部品がなければ自らの手でつくる」、と真逆に位置している。
作業スペースの一番奥、名取に案内してもらった部屋に入ると、削り、加工など簡単な部品を自作できる工作機械があった。
「カムシャフトやレンズ分解用に自作した工具など、できるものは可能な限り自作してきました。いずれも図面がないですから正確にサイズを計測し、この工作機械を使って」という名取に、「なぜそこまで」という問いをぶつけるとこんな答えが返ってきた。
「入社した時から先輩たちはそうやっていましたからね。部品がなければつくる。最後まで諦めない。それはここでは普通のことなんです」